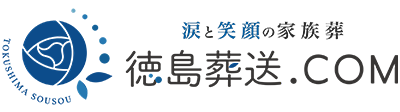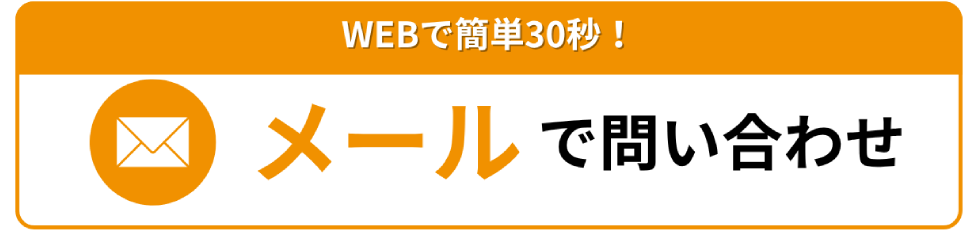-
身内だけの家族葬で香典は必要?家族葬の基本的な特徴やトラブル回避のためのポイントを徹底解説します2025.10.02

身内だけの少人数で行う家族葬は、参列者に気を使わずに済み、故人とのお別れをゆっくり行える葬儀の形式として近年増えています。
参列者が少ないことから「香典を持っていくべき?」という参列者側の不安、そして喪主側にとっても「香典を辞退した方がいいの?」「伝え方はどうすべき?」という悩みを持つことが多いようです。
親戚同士だから気を使わずに済むかと思いきや、お互いの認識の違いから思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。
そこで今回の記事では、身内だけの家族葬における「香典」について、参列者側・喪主側と両方の視点からお話していきたいと思います。
身内だけの家族葬、香典どうする?迷いやすい家族葬の基本とマナーとは?
身内だけの家族葬における基本的なマナーについてお話していきます。
家族葬とはどんな葬儀か
家族葬は、一般的な参列者を呼ばず、故人の家族や親など身内を中心として行われる小規模な葬儀です。人数は少なければ10人未満、多くても30人以内程度のことが多いですが、葬儀の流れは一般的な葬儀とほとんど同じです。
近年は、「家族だけでゆっくりと見送りたい」「故人が終活にて希望していた」など、さまざまな理由から家族葬を選ぶ方も増えてきました。
また、家族葬は家族や親戚を中心としますが、特に親しい友人も参列するケースがあります。
“香典辞退”という連絡があったら持参しなくても大丈夫
小規模な葬儀のため、喪主側が「香典を辞退する」という意向を示す場合もあります。供花や弔電など、不祝儀全般を辞退するご遺族もいらっしゃいます。
そんな連絡があった際は、香典を渡さないのがマナーです。
遺族側が「香典を辞退する」という言葉の裏には、できるだけシンプルな葬儀にしたいという気持ちや、香典返しの手間をかけたくないなどの事情があることが多いです。
香典を辞退すると言われたときは、遺族の意向に沿うようにしましょう。
一般葬と同様に香典を持参するのがマナー
香典辞退の連絡がなければ、基本的に葬儀当日には香典を持参しましょう。香典には故人への弔いの意味や、遺族の金銭的負担を支援する意味も込められています。
特に、昔ながらの伝統を重んじる人にとっては、香典を送ることは大切なマナーです。辞退の意向がないときは香典をきちんと包みましょう。
身内だけの家族葬で香典がいらないケースとは
自分が喪主である場合は香典を包む必要がありません。そのほか、学生で収入がない場合は一緒に参列する親御さんが香典を包むため、本人の分としては不要と考えられるケースが多いです。
葬儀に参列できなければどうすべき?
家族葬の参列者は喪主や遺族が中心となって決めるため、たとえ親族であっても参列できない場合もあります。
遠方などの事情で当日葬儀に参列できないこともあるでしょう。
後から弔問をして香典を渡すケースもありますが、お葬式で香典を辞退しているなら、後日の訪問でも香典を辞退している可能性が高いです。
弔問する際、あるいは郵送する際には事前に遺族に連絡をし、受け取ってもらえるかの確認をした方がいいでしょう。
身内だけの家族葬で香典を用意する場合の金額相場や渡し方の事前知識とは
次に身内だけの家族葬における香典の相場や渡し方についてのポイントをご紹介します。
金額の相場をふまえる
香典は一般的な金額の相場をふまえることが大事です。故人との関係別の香典金額目安は以下の通りです。
・両親の場合:5~10万円
・祖父母の場合:1~5万円
・兄弟・姉妹の場合:3~10万円
・おじ・おばの場合:5千円~3万円
・それ以外の親族の場合:5千円~2万円
がだいたいの目安となっています。
故人との関係が深い場合や、ご自身の年齢が高くなるにつれて、多めの香典を包むことが一般的です。しかし、たとえ血縁関係が深くても疎遠だった場合などは、あまり多く包まなくてもいいという考え方もあります。
また、地域によっても相場が異なることもあるため、身内だけの家族葬では自分以外の人と相談して金額を決めるのもいいでしょう。
同じ立場の人がいれば、金額が大きく異ならないように事前に相談して香典額を決めることをおすすめします。
香典袋の表書きの書き方
お通夜や葬儀場で渡す香典の表書きは、宗教によって異なります。
仏式の場合「御霊前」や「御香典」と書くのが一般的です。
人は亡くなった直後は魂があの世へ行く途中ですが、四十九日を過ぎると次の世界に生まれ変わると考えられています。そのため、葬儀の際に持参する香典袋には「霊」の文字が使われるのです。
ただ、浄土真宗の場合は、亡くなってすぐに仏になるとされ、「御仏前」という表書きになります。
参加する家族葬の宗派について分からない場合は、「御霊前」と書くのが無難です。
香典袋に入れるのは古い札
新札を包むと「準備していた」という印象を与えてしまうため、古いお札を香典袋に入れるのがマナーです。だからと言って極端に汚すぎてボロボロのお札は失礼にあたるため注意しましょう。
古い札を探すのもいいですが、もし新札しかない場合は、折り目をつければ大丈夫です。
渡すタイミングにも注意する

通夜、葬儀や告別式などのどちらかで香典を渡しましょう。香典は、一回だけお渡しするのがマナーです。
通夜にも葬儀にも参列するからと言って、香典を2回渡す必要はありません。そのため、どちらにも参列する場合には、葬儀の日に渡すのが一般的です。
葬儀場の受付にてお渡ししましょう。
また、通夜にしか参列できないときは、お通夜の日に持参することをおすすめします。
身内だけの家族葬で香典を辞退したい場合の伝え方と注意点
書面にて通知する際には、「辞退する」という文言だけでなく、故人の遺志であることなどを伝えることが大事です。
以下のような文例をご参考ください。
・故人の遺志により、香典・供花・供物などはご辞退申し上げます
・誠に勝手ながら、御香典・御供花・御供物は固くご辞退申し上げます
曖昧に伝えると、香典を持参してくる方も多いです。喪主側の気持ちとして、はっきりと辞退を伝えておくことがポイントです。
家族葬で香典返しは必要?失礼にならないためのタイミングや相場、対応例について

次に喪主側で知っておきたい香典返しの必要性について、いくつかポイントをお話していきます。
家族葬でも香典返しをする
家族葬であっても一般葬であっても、故人のために参列してくだった方には感謝の気持ちとして香典返しの品物をお渡しするのがマナーです。受け取った場合には、かならずお礼の品物を贈るようにしましょう。
香典返しのタイミングは「四十九日」を過ぎたとき
仏教では、亡くなってから四十九日までの期間は「忌中」とされ、四十九日法要をもって「忌明け」となります。
このタイミングで、
・無事に四十九日法要を終えたことの報告
・故人を偲んでくれたことへの感謝
・葬儀への参列、香典をいただいたことへのお礼
などを伝える書面とともに香典返しをお渡しするのが一般的です。
相場は“半返し”
一般葬でも家族葬でも、基本的な金額相場は“半返し”です。いただいた金額に対して、半分ほどの金額でお返しの品物を選びましょう。
会葬返礼品と混同しない
香典の金額にかかわらず、葬儀に参列してくれたことへの感謝の意味」が込められているのが会葬返礼品です。一般的には500~1000円未満ほどの日用品を選ぶことが多く、タオルや海苔、お菓子などが多い傾向となっています。
一方、香典返しは香典の金額に応じて渡すものです。
「即日返し」という選択もある
本来は、四十九日を過ぎた後にお渡しするのが香典返しです。
しかし、品物を持って訪問したり、配送の準備を考えると手間と感じる人もいて、最近は葬儀の当日にお返しの品物を渡す「即日返し」をする人が増えてきました。
特に、参列人数が少ない家族葬の場合は、法事の当日に渡すと手間が少ないと考えられる傾向です。
ただ、香典の金額が事前に分からないため、想定より多くいただいたときは後日改めて香典返しを贈る必要が生じるかもしれないため注意しましょう。
身内だけの家族葬で発生しやすいケース別トラブルとその対応方法

基本的には身内で行う家族葬ですが、故人の生前の希望が反映されていたり、遺族の負担を減らす意味合いなどが込められています。ただ、参列者が身内を中心としていることから、香典に関する世代の価値観の違いなどが下人で、予想外のトラブルを生むケースもあるようです。
ケース①:香典を辞退していたのに受け取ってしまった
【事例の内容】
お父様が亡くし、身内だけの家族葬を選んだAさん。葬儀に関する連絡は、親族数名に口頭で「家族葬で小規模であるため、香典を辞退する」と伝えていました。
しかし、実際にはその意向が十分に伝わらなかったようで、昔ながらの風習を大事にする親族の一人が「辞退されたけど持参がマナー」と感じ、持ってきた人の香典を受け取ってしまいました。
ところが、「自分は持ってきたのに持ってこない人がいる」と不公平感を抱いた参列者同士で気まずい雰囲気となってしまったのです。
【対策】
口頭だけで伝えることで、「香典を辞退したい」という気持ちが完全に伝わらないことも多いです。そこで、電話だけでなく、文書やメールでも伝えることがポイントとなってきます。
また、それでも持ってきた人の香典を受け取ってしまうと、持参しなかった人との間に不公平感が生まれることも…。
今後の円滑な親戚付き合いのためにも、香典を持参した人には「お気持ちだけ受け取らせていただく」ことを丁寧に伝えて辞退して対応しましょう。
ケース②:香典を持参しなかった人が悪く言われていた
【事例の内容】
喪主から「香典を辞退する」という話を聞いていたBさんは、その意向にしたがい、香典は持参しませんでした。
しかし、当日、実際には自分以外の参列者の多くが香典を持参し「香典を持ってこないなんて」と陰口をたたかれてしまったのです。
喪主の意思を尊重しただけのBさんが、悪く言われてしまうことになりました。
【対策】
参列者のなかには、喪主が言っている「香典は不要」という言葉を「本当は受け取りたいけれど遠慮しているだけ」と誤解しているケースもあるようです。
香典辞退を伝える際には、「香典辞退は故人と遺族の意思である」「お気持ちだけで十分」「皆さまに一律に願いしていること」という具体的な内容を補足し、参列者同士でトラブルを生まないように貫性のある伝え方をすることが大事です。
まとめ
一般的な葬儀よりも少人数の家族葬は、参列者も主に身内が中心。人数が限られているため、一人ひとりの対応や配慮がより重要になります
「香典を辞退する」と喪主から申し出がなければ、参列者は基本的に香典を持参するのがマナーです。香典には、故人が亡くなったことを心から偲び、遺族への気持ちとしての意味合いも含まれています。
しかし、香典返しの手間などから「香典を辞退する」というケースもあり、その際は喪主の意向をくみとって持参せずともいいでしょう。
また、香典の辞退については、喪主側が言葉や文章で伝えても、残念ながら真意が伝わらずにトラブルの火種となるケースがあるため注意が必要です。
香典に関するトラブルは、ちょっとした伝え方の違いから発生することが多いです。事前に丁寧に案内をすること、そして「一貫した対応」を心がけることで、不要な誤解や不満を防ぐことができるでしょう。
葬儀には多くのご不安がつきものですが、私たち徳島葬送.COMが一つひとつ丁寧にサポートいたします。
「今すぐではないけれど、いざという時のために知っておきたい…」という方には、資料請求や無料の事前相談がおすすめです。お気軽にご利用ください。

監修者
徳島葬送.COM 代表取締役
田岡 博憲(たおか ひろのり)【保有資格】
・厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター
・日本海洋散骨協会認定 海洋散骨アドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士
・終活協議会認定 終活ガイド
徳島での葬儀に携わり15年以上の経験があり、四国で初めて葬祭関連有名全国誌の月刊終活に特集していただいております。徳島での終活・葬儀・供養の事はすべてお任せください。
- 葬儀の豆知識一覧
-
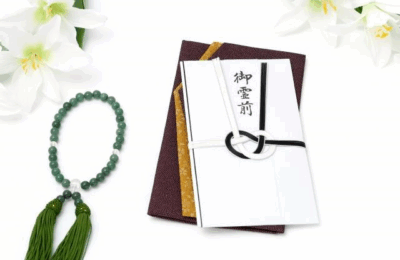 2025.10.02身内だけの家族葬で香典は必要?家族葬の基本的な特徴やトラブル回避…
2025.10.02身内だけの家族葬で香典は必要?家族葬の基本的な特徴やトラブル回避… -
 2025.10.01葬儀に事前相談は必要?事前相談の重要性やメリット、流れやポイント…
2025.10.01葬儀に事前相談は必要?事前相談の重要性やメリット、流れやポイント… -
 2025.06.27【徳島の葬儀】葬儀で喪主がやることとは?葬儀開始前からの全体像と…
2025.06.27【徳島の葬儀】葬儀で喪主がやることとは?葬儀開始前からの全体像と… -
 2025.06.27【徳島の葬儀】香典返しの相場や品物の選び方とは?返礼品との違いに…
2025.06.27【徳島の葬儀】香典返しの相場や品物の選び方とは?返礼品との違いに… -
 2025.06.27【徳島の葬儀】生前からの葬儀の準備はやった方がいい?事前準備の背…
2025.06.27【徳島の葬儀】生前からの葬儀の準備はやった方がいい?事前準備の背… -
 2025.04.21徳島で行う一日葬|1日で葬儀が終わる一日葬とは?流れや基礎知識、…
2025.04.21徳島で行う一日葬|1日で葬儀が終わる一日葬とは?流れや基礎知識、… -
 2025.02.25近年の葬儀で増えている“直葬”とは?一般葬との違いや費用相場、メ…
2025.02.25近年の葬儀で増えている“直葬”とは?一般葬との違いや費用相場、メ… -
 2025.02.06失敗しない葬儀日程の決め方|友引・仏滅の注意点や葬儀スケジュール…
2025.02.06失敗しない葬儀日程の決め方|友引・仏滅の注意点や葬儀スケジュール…
-