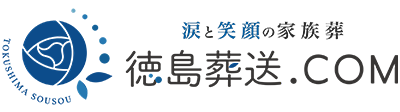-
【徳島の葬儀】葬儀で喪主がやることとは?葬儀開始前からの全体像と喪主の心構えを徹底解説2025.06.27

葬儀への参列経験はあっても、喪主の経験が豊富という方はほとんどいないのではないでしょうか。そのため、家族を亡くした深い悲しみのところ、喪主という大役を任されると不安や焦りといった複雑な気持ちが入り混じるものです。
喪主は葬儀の中心的な存在ですから、やることがかなり多く、慌ただしくなりがちです。後悔のない葬儀のためには全体的な流れや心構えを知っておくことも大事です。
今回の記事では、喪主のやることを「葬儀前・葬儀当日・葬儀後」というステップに分け、詳しく解説していきます。
喪主がやることリスト:葬儀前から葬儀後までの全体像
葬儀で喪主をやる場合、故人が亡くなった直後から慌ただしく動かなければなりません。全体像を掴むために、葬儀前から葬儀にかけての流れとともに“やること”をお話していきます。
【葬儀前】
葬儀社を選定する
ご臨終の後、喪主が初めにやることは「葬儀社の選定」です。
病院で亡くなると一時的に霊安室で安置されます。しかし、長く病院にいることはできないため、なるべく早く“安置場所”へと運ばなければなりません。
だいたい2~3時間以内には手配を進めるのが理想です。
主治医から死亡診断書を取得する
医師に依頼して死亡診断書を取得するのも喪主のやることのひとつです。
搬送の際だけでなく、火葬や手続きなど、これからさまざまな場面で必要なので大事に保管しておきましょう。
退院の手続き(病院に入院中に死亡した場合)
葬儀社を選定後、葬儀社の担当者が病院に来るまでの間、退院の手続きを進めます。入院費の支払いは後日の清算となることが多いですが、詳細については各病院の対応に合わせましょう。
遺体を安置場所まで搬送する
遺体を搬送するのは、依頼した葬儀社の車です。
安置場所には、自宅や葬儀社の霊安室、斎場、寺院などさまざまなところがあります。
檀家となっている方は寺院の本堂で葬儀をするケースもあります。寺院によって詳細は異なりますが、遺体を寺院に安置できる場合もあるので直接寺院に確認をしましょう。
訃報の連絡と参列者の調整をする
親戚や友人など、特に親しい人へは早めに連絡をしましょう。電話・メールといった連絡手段がありますが、参列してほしい人には電話の方が早く伝わりやすいです。
葬儀の日取りを決める関連もありますので、寺院にも早めに連絡しておくと安心です。職場や学校関係への連絡は、葬儀関連の日程が決まってからでもいいでしょう。
また、参列者の人数を把握することも大事です。思いのほか参列人数が多いときは、会場変更をともなう場合もあります。急遽、会場変更があうと混乱しやすいので、すぐに連絡を取り合えるようにしておくことをおすすめします。
葬儀社と打ち合わせをする
葬儀社のスタッフと葬儀プランや日程、料金など葬儀全般の内容を細かく打ち合わせます。打ち合わせは基本的に葬儀社から詳しい指示があるので、流れに沿って話し合っていきましょう。
初めての喪主は疑問も多いはずです。打ち合わせ中に不安点があれば、すぐに質問して解決しておきましょう。
死亡届を役所に提出する
死亡届は、喪主や遺族がやるほか、葬儀社が代行してくれるケースもあります。
届出の際に医師から受けとった死亡診断書が必要ですが、後のさまざまな手続きでも使うため、提出前に必ず複数枚のコピーを取っておきましょう。
遺影や供花の準備・会葬品や会食などの手配をしておく

葬儀に間に合うように、遺影の用意もしなければなりません。故人の生前の姿が分かる写真を選ぶことが大事です。
遺影に使う写真は「何年前までのもの?」と疑問に思う方が多いですが、「5年くらい前までの写真」が良いとされています。ただ、なければそれ以前の物でも構いません。大切なのは、「写真が鮮明であること(ぼやけていないこと)」と「故人らしい表情のもの」を選ぶことです。
また、なかにはスナップ写真しかないという方もいて「遺影に使えるのだろうか」と心配される方もいますが、修正技術が進歩した昨今は、遺影用に修正してもらうこともできます。
そのほか、供花や参列者にお渡しする会葬品や当日の会食の手配もします。棺におさめる物なども準備しておきましょう。
かつては忌明け後に香典返しをするケースが主流でしたが、最近は葬儀当日に香典返しの品物を渡すケースもあります。その場合、会葬品だけでなく香典返しの品物も選んでおかなければなりません。
僧侶に渡すお布施の準備も必要です。現金で渡すものですから、早めに準備しましょう。「お布施の金額はいくら…?」「どんな封筒に入れるのか」など不安点は葬儀社にも相談して確認することが大事です。
葬儀当日までに準備する物に関しては、詳しくは葬儀社のスタッフからの指示があります。不明な点はすぐに確認しておくことで、当日慌てることなくスムーズに進みます。
【お通夜、葬儀、火葬当日】
葬儀社との打ち合わせ
お通夜、葬儀の当日は、喪主は「開始1~2時間前」を目途に葬儀場・火葬場に行きましょう。供花の並べる順番や、弔電を紹介する順番なども事前に打ち合わせをしなければなりません。
また、葬儀の規模によっては、受付を親族などの参列者にお願いするケースも少なくありません。受付に立ってもらう人には、葬儀当日は早めに会場に来ていただくように案内しておくことが大事です。
僧侶への挨拶、お布施をお渡しする

僧侶への挨拶、お布施のお渡しも喪主の務めです。
葬儀の読経と戒名へのお礼となる“お布施”のほか、御膳料・御車代などもお渡ししましょう。お布施をお渡しするタイミングは「葬儀前」か「葬儀後」のどちらかになります。
金額については、地域性や宗派でも大きく異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
参列者への挨拶
故人とのお別れに来てくれた参列者が不安を持たずに快適に過ごせるように気を配ることが大事です。
また、葬儀では喪主挨拶があります。時間的には1~3分ほどと短めでも大丈夫ですが、参列者への感謝の気持ちや故人のエピソードを伝えられるように事前に考えておくと安心です。
【葬儀後】
葬儀費用の支払い
葬儀が終わると、葬儀社から費用に関する連絡があります。支払いの期限を過ぎないように、なるべく早めに清算することをおすすめします。
葬儀関連の領収書は、無くさないように保管しておきましょう。
香典返しの手配
葬儀の参列者からいただいた香典に対する品物“香典返し”を手配しましょう。通常は、四十九日を過ぎたタイミングでお渡しします。いただいた金額の「半分~1/3」を目安に品物を選ぶのがマナーです。
供養方法の決定
遺骨の供養についても決めなければなりません。
選択肢としては、
・先祖代々のお墓に納骨する
・新たにお墓を購入する
・永代供養をする
などの方法があります。
すでにお墓がある際は、四十九日法要に合わせて納骨する方が多いです。菩提寺と相談しながら納骨の日取りを決めましょう。
納骨には期限はないものの、新しくお墓を建てるときは一周忌法要にあわせる方もいます。
各種手続き
葬儀後は、
・年金受給中の場合は停止の手続き
・葬祭費の申請
・賃貸物件居住中の場合は清算・解約手続き
・保険金の受け取りに関する申請
・名義変更、解約手続き
・携帯電話、インターネットの解約
など故人に関する各種手続きを進めていきましょう。
手続き漏れがないようにリストを作っておくと安心です。
また、遺品整理についても注意が必要です。明らかに不用品であるものを除き、時計やアクセサリー、絵画など高額な物は「相続の対象」となるケースが多いです。
後々のトラブルを避けるためにも、喪主はもちろん、相続人同士で慎重に進めていくことが大事です。
初七日法要・四十九日法要
ご逝去の後、7日目には「初七日法要」、49日目には「四十九日法要」が行われます。ただ、初七日法要は、近年では葬儀当日にやることが増えています。
葬儀後の大きな節目となり、忌明けとなるのが「四十九日法要」です。四十九日法要は、参列者が集まりやすいように「四十九日」よりも前の土日などに行うケースも多いです。
誰に参列してもらうか、会食の席を設けるのかなども考えておくとともに、僧侶の都合もあるので早めに日程を調整しておきましょう。
喪主の大切な役割から考える「喪主を務めるべき人」とは?

喪主は葬儀の中心的存在です。
主に、
・葬儀の準備と進行の確認
・葬儀社との打ち合わせ
・僧侶への連絡
・参列者への対応
・香典のとりまとめ
・葬儀費用の支払い
などさまざまな役割があります。
打ち合わせや電話連絡なども多く含むことから、責任感を持ち進めていける人がふさわしいとされています。
移動なども速やかに行う必要があるため、高齢の方、持病のある方などは難しいかもしれません。負担を軽減できるように、体力のある方の方がいいでしょう。
ただ、一般的には故人と近しい血縁関係者が喪主を務める傾向です。終活をしていた方で、遺言やエンディングノートに喪主の希望が記載されていたらそれに従いましょう。
夫婦なら配偶者が務めるのが一般的です。しかし、年齢や体調なども相まって「本来喪主を務めた方がいいケースだけど負担が大きく難しい」といったケースもあるでしょう。そのような場合には子供や孫、兄弟など故人と近しい存在の信頼できる親族にお任せするなど、ケースバイケースです。
独身の方なら、親や兄弟姉妹、甥・姪などが一般的です。
喪主は、葬儀の準備段階から、葬儀社との打ち合わせや各種手配、参列者への対応など細かなことまで気を配る必要があります。
喪主ひとりでは実際には難しいので、遺族が協力し合いながらサポートしていくことが理想的です。
喪主としてのマナーと心構えとは?
次は、喪主を務める際のマナーと心構えについてです。
身だしなみに注意する
喪主であることを意識し、参列者に対し不快な気持ちにさせない身だしなみを心がけましょう。特に、女性の場合、派手な髪型やアクセサリーは目立ちます。
参列者に対しても失礼にあたらないように、清潔感と“控えめ”を基調とした服装がマナーです。
参列者の状況に合わせた配慮をする
葬儀には、遠いところからいらっしゃる方、足が悪いのに来てくださる方などさまざまな方がいらっしゃいます。
遠方からはるばる来られた方に対しては、ひと声挨拶をしつつ、特別な配慮も考えるといいでしょう。
また、高齢の方や足腰の悪い方などに対しても、椅子をお出しするなど状況に合わせて気配りをすることも必要です。
故人を“偲ぶ”気持ちを忘れずに
忙しく動き回ることで焦りが生まれるかもしれませんが、故人を偲ぶ気持ちを忘れずに喪主の仕事を務めることが大事です。ひとりで全てを背負おうとせず、家族や親族にも頼りつつ、葬儀社のスタッフにも相談しながら進めていきましょう。
まとめ~喪主の役割を理解した葬儀を
喪主は葬儀前から葬儀後までやることが多数あります。
「初めて喪主を務める」という方は、家族が亡くなった悲しみに直面し、喪主という大役への不安から体調を崩されることもあります。混乱しないように“やること”をチェックリスト化しながら、段取りをおさえておくことが大事です。
また、葬儀は形式にあわせてマナーを守りながら行わなければなりません。ただ、すべてをひとりで抱え込むと負担が大きくなります。喪主を中心的な存在としながらも、家族や親族とも助け合いながら故人とのお別れを進めていきましょう。
葬儀の準備は多くのご不安がつきものですが、私たち徳島葬送.COMが一つひとつ丁寧にサポートいたします。
「今すぐではないけれど、いざという時のために知っておきたい…」という方には、資料請求や無料の事前相談がおすすめです。お気軽にご利用ください。

監修者
徳島葬送.COM 代表取締役
田岡 博憲(たおか ひろのり)【保有資格】
・厚生労働省認定 一級葬祭ディレクター
・日本海洋散骨協会認定 海洋散骨アドバイザー
・相続診断協会認定 相続診断士
・終活協議会認定 終活ガイド
徳島での葬儀に携わり15年以上の経験があり、四国で初めて葬祭関連有名全国誌の月刊終活に特集していただいております。徳島での終活・葬儀・供養の事はすべてお任せください。
- 葬儀の豆知識一覧
-
 2025.06.27【徳島の葬儀】葬儀で喪主がやることとは?葬儀開始前からの全体像と…
2025.06.27【徳島の葬儀】葬儀で喪主がやることとは?葬儀開始前からの全体像と… -
 2025.06.27【徳島の葬儀】香典返しの相場や品物の選び方とは?返礼品との違いに…
2025.06.27【徳島の葬儀】香典返しの相場や品物の選び方とは?返礼品との違いに… -
 2025.06.27【徳島の葬儀】生前からの葬儀の準備はやった方がいい?事前準備の背…
2025.06.27【徳島の葬儀】生前からの葬儀の準備はやった方がいい?事前準備の背… -
 2025.04.21徳島で行う一日葬|1日で葬儀が終わる一日葬とは?流れや基礎知識、…
2025.04.21徳島で行う一日葬|1日で葬儀が終わる一日葬とは?流れや基礎知識、… -
 2025.02.25【徳島の葬儀】近年の葬儀で増えている“直葬”とは?一般葬との違い…
2025.02.25【徳島の葬儀】近年の葬儀で増えている“直葬”とは?一般葬との違い… -
 2025.02.06【徳島の葬儀】失敗しない葬儀日程の決め方|友引・仏滅の注意点や葬…
2025.02.06【徳島の葬儀】失敗しない葬儀日程の決め方|友引・仏滅の注意点や葬… -
 2025.01.07家族の死亡後にやらなければならない手続きは?死亡直後からの流れに…
2025.01.07家族の死亡後にやらなければならない手続きは?死亡直後からの流れに… -
 2024.11.26【徳島の葬儀】親族の葬儀に香典はいくら包む?親族別の金額相場や知…
2024.11.26【徳島の葬儀】親族の葬儀に香典はいくら包む?親族別の金額相場や知…
-
お問い合わせ
葬儀のご相談やご質問、
オンライン事前相談の申し込みなど
お気軽にお問い合わせください。